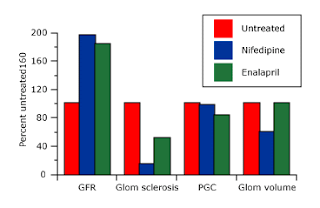Canagliflozinの治験CANVASと、続編CANVAS-Rスタディの結果がNEJMにでた(DOI:10.1056/NEJMoa1611925)。昨年
書いたEMPA-REGと似た結果で、心血管系イベントが有意に下がったといっても、心不全がRR 0.78(信頼区間0.67-0.91)なほかは信頼区間が1.0をまたいでしまう。血圧がさがり体重がへるのもEMPA-REGと同様だ。
気になることが3点ある。1点目はサブ解析の結果だ。人種ごとに結果を見ると白人の心血管系イベントRRは0.84(0.73-0.96)で有意、黒人はRR 0.45だが信頼区間は0.19-1.03でギリギリ1をまたぐ。そしてアジア系はRR 1.08(信頼区間0.72-1.64)で、なんとプラセボと変わらない。がっかりだ。
このスタディは30カ国でおこなわれたのでアジア系は全体の13.4%とそんなに少なくはない。有意差が出なかったというのは信頼できるデータかもしれない。そのうち「CANVAS-J」みたいな日本のデータがでるだろうが(パンフレットの表紙はこんな感じか?写真)、この結果と余りに違わないか検証する必要がある。
2点目は腎予後だ。アルブミン尿の進展、eGFRの低下、透析や腎による死亡はいずれも介入群で数字上はめざましく低い(CIが余裕で1.0未満)。しかしアブストラクトにもあるように、これらの結果は彼らが事前に計画した仮説検証モデルによれば統計学的に有意とはいえなかった。それで結論はpossible benefitと言っている。まして、人種差があるかもわからない。
SGLT2阻害薬のクラスはどれも腎症予防効果があるように言われているし、その期待に水を差すつもりはない。武器は多いほうがいい。適応のあるひとに期待して使うことも、間違っていないと思う。ただ結果が「possible effect(効くかもしれない)」なことは知っておきたい。
ここでやめておいても「効く(らしい)!」で(特に日本では)売れるだろうに、「結局ちがった…」というリスクを負ってでも、この会社と研究者は白黒つけに腎予後のCREDENCE(信用という意味)スタディを走らせている。金儲けだけじゃなくて、ほんとうに結果を追求したいのならplausibleなだけでなくapplaudableと思う。
だからこそ突き詰めてほしいのが3点目、副作用についてだ。以前にFDAが
警告していたが、やはり介入群で有意に足切断例がおおかった。ほとんどは趾レベルだが、気持ちが悪いし、いつか足元をすくわれそうだ(写真は絵にかいた穴)。糖尿病患者さんにとって末梢動脈疾患と足壊疽は大問題であり、この仕組みがわかって新しい治療になるかもしれないから研究を期待したい。
また、日本ではまだあまり知られていないようだから書いておくが、SGLT2阻害薬には血糖正常DKA(eDKA)の副作用がある。すい臓のα細胞にSGLT2があるのでグルカゴン産生に傾く。私も
書いたが、代謝のお話だし、詳しくは日本の先生方がお書きになったこちらの
論文を参照してほしい。こちらはここまで分かっているし、足壊疽も調べたら何か分かるはず。
[2019年4月18日追記]上に紹介したCREDENCEの結果が、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに今日
でた(DOI: 10.1056/NEJMoa1811744、無料で読める)!
eGFRが30-90ml/min/1.73m2(30-60の患者が60%、中央値は56)でアルブミン尿(300-5000mg/gCr、中央値は927)のあるDKD患者(HgbA1cは6.5-12%、ドイツのみ6.5-10%、中央値は8.3)を対象にして、カナグリフロジン100mg/日とプラセボを比較したこの試験は、アウトカムに早期から明確な差が出て2.6年で「うれしい」中断となった。
プライマリ・アウトカムは①末期腎不全(30日以上の透析、腎移植、30日以上のeGFR15未満)、②Cr増加(ランダム化前・時から2倍以上が30日以上)、③腎・心疾患死亡を合わせたものだった。これが介入群で43.2/1000人・年、プラセボ群で61.2/1000人・年だった。
もちろん介入群で有意に低い。
つまり、こういうことだ。
絶対リスク減少(ARR)は61.2/1000と43.2/1000の差で、1.8%/人・年。1000人を2.5年治療すると、1000×0.018×2.5で45のアウトカム・イベントを予防できることになる。これを言い換えたものがNNT(number needed to treat、何人に治療すればイベントをひとつ回避できるか)というが、CREDENCEで計算されたCanagliflozinのNNTは:
「22(95%信頼区間15-38)」だった。
アトルバスタチン10mgを加えた時の心血管イベント/死亡予防効果をしらべたASCOT-LLA(Lancet 2003 361 1149)では、3.3年間治療して得られるNNTが98だったというから、かなりよい数字といえよう(
下表は、Oxfordの関係者が独自にエビデンスを鑑定するサイトBandolierから)。
では、誰に何がどう良かったのか?
まず「誰に」であるが、サブ解析ではeGFRは60未満の群(数字上は30-44よりは45-59のほうがいっそう有意)、アルブミン尿は1000mg/gCr以上の群で有意差がみられた。スタディが5000mg/gCr以上を除外したのは効果がでないことを怖れたからと思われるが、1000mg/gCrではむしろ有意差が出なかったので、蛋白尿がある程度あったほうが効果が期待できるのかもしれない。
また特筆すべきは、CANVASでは信頼区間が1にかかってしまったアジア系(コホート全体の19%:アジアからは中国が参加している)が今回ハザード比0.66で、95%信頼区間も0.46-0.95だったことだろう。
つぎに「何が」についてであるが、個々のアウトカムはいずれも介入群で低かった。ただし細かく見ると、ハザード比の95%信頼区間が0.99未満だったのはCr上昇とeGFR15未満で、透析・移植と心血管死亡はそれぞれ0.55-1.00、0.61-1.00であった。公平に言ってフォロー期間が短く実数が少なかった可能性を最も疑う。
最後に「どう」であるが、これが解明されるのはもう少し先になりそうだ。糸球体ろ過圧から尿細管代謝まで、論文の引用文献11-17にさまざまな推察が載っているので、アクセスのある方は読んでみるとよいだろう。
11:Circulation 2014 129 587
12:Physiol Rev 1990 70 665
13:JCI 1987 80 670
14:Curr Hypertens Rep 2019 21 12
15:Eur J Endocrinol 2018 178 R113
16:Cell Rep 2018 25 677 (e4)
17:ACKD 2018 25 244
それでは、副作用についてはどうか?
上にも書いた足切断や骨折のリスクには有意差がなかった。DKAはやはり有意に高かったが、使い方を分かってきたせいか11件/2200人だった(サプリメントによれば1件が血糖250mg/dl未満のいわゆる「eDKA」であった)。
尿路・性器感染症についてはサプリメントに書かれているが、尿路のほうは有意差がなく、性器真菌感染症は男性で28件/1439人、女性で22件/761人と有意に高かった。
腎臓内科のフィールドで、しかもDKDという本丸で、ここまで強いエビデンスが出たのは本当に久しぶりだと思う。約束どおり、investigatorの皆さまに拍手を送りたい。近位尿細管などいままで未解明だった領域に臨床応用が進む第一歩。今後もこの調子で行けば、きっとキセキは起きる。
[2019年5月24日追記]上記CREDENCEの結果はメルボルン開催のWorld Congress of Nephrology(WCN)でPIのVlado Perkovic先生から発表されたが、そのとき会場の聴衆が本当にスタンディング・オベーションしていたことが分かった。
スタンディング・オベーションは、プライマリ・アウトカムを紹介する時、あえてP値のない2本のグラフをスライドにして、そのあとからP値が「0.00001」だと発表したときに起こったそうだ。いわれてみれば、驚異的な値だ。
もう読者は推察されているだろうが、これもKSN2019で得た情報だ。APSN/KSN CMEで、APSN会長でもある(WCNにもいらっしゃった)南学正臣先生が、酸化ストレスと低酸素のAKIやDKDへの影響についてのレクチャのなかで紹介してくださった。
もちろんレクチャはスタンディング・オベーションだけでなく、「何が良かったか?」「これからは?」など一歩も二歩も踏み込んだもの(写真は、バルドキソロン国内第三相試験、AYAMEの紹介)だったが、それについては稿を改めて紹介する予定だ。