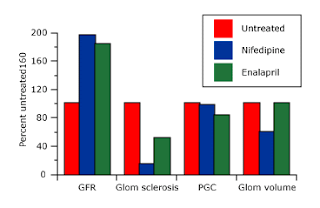3. 結果
まず、2007年から2017年までに腎レジストリに登録された患者は30180人。そのうち、eGFRが30ml/min/1.73m2未満になるT0時点とその前(2年間の80%日数以上)ACEI/ARBが処方されていたのは10254人。なお18歳未満・移植後・データ不備がある患者などは除外している。
そのうち、ACEI/ARBを中止されたのは1311人、継続していたのは8484人だった(足して10254人にならないのは、T0から6ヵ月後時点のため)。中止群が圧倒的に少ないのは、中止後ACEI/ARBが再開されていた患者(57%にのぼる)を除外しているからであろう。
このコホートについてウェイティングし、中止群は9820.1人、継続群は9772.4人となった。
「患者」は平均約72歳、女性4割、血圧約138/75mmHg(スウェーデンはフランスと同じく人種の統計がない)。既往は高血圧9割、心筋梗塞2割、心不全3割、PAD1割、糖尿病5割、COPD2割、がん1割であった。内服はβブロッカー7割、CCB6割、利尿薬8割、スタチン6割、抗血小板薬4割。
両群間に有意差はなかった。というか、そのように調整した。
次にアウトカムであるが、5年間絶対リスクは総死亡・MACEは中止群で有意に高かった。しかし、前編の米国スタディと異なり腎代替療法(KRT)は継続群で有意に高かった。
中止群 継続群
総死亡 54.5% 40.9%
差 13.6%(7-20*)
MACE 59.5% 47.6%
差 11.9%(5.7-18*)
KRT 27.9% 36.1%
差 -8.3%(-12から-3.6*)
*95%信頼区間
総死亡とMACEは中断群と継続群の差が時間と共に開いていくグラフが得られた。いっぽう、KRTは最初中断群のリスクがわずかに高く、3年くらいして中断群が頭打ちとなり継続群の直線的なラインとクロスしていた。
 |
| JASN 2021 32 424 図2を元に作成 |
また、総死亡・MACEの5年間RMSTは中断群で有意に短く、KRTは中断群で数字上長いが有意差はなかった(単位は、月)。
中止群 継続群
総死亡 44.3 47.9
差 -3.6(-5.4から-1.8*)
MACE 41.4 44.7
差 -3.3(-5.3から-1.4*)
KRT 48.9 48.1
差 0.8(-0.8から2.5*)
*95%信頼区間
eGFRが20-30、20ml/min/1.73m2未満のサブコホートについての解析でも「総死亡とMACEは中断群で高く、KRTは中断群で有意に低い」という結論に変わりなかった。
また年齢性別・既往・カリウム値・蛋白尿が交絡因子かどうかもAERI(absolute excess risk due to interaction)により検討されたが、カリウム値が5mEq/l未満か以上かがKRTリスクに影響していただけだった(ちなみに、血圧の影響は解析されていない)。
4. まとめと感想
①まとめ
相関でしかないが、このスタディから導かれるのは「腎臓内科医が診れば、死亡とMACEのリスクを取ってACEI/ARBを中止すると腎代替療法を遅らせることができるかもしれない」だろう。
腎臓内科外来にくる患者は「とにかく透析にはなりたくない」と初診されることが多い。そして医者側も、eGFRのカーブを図解して「透析になるまでの期間をできるだけ遅らせましょうね」と言うことが多い(筆者も、そう言っている)。
その意味でこの結果は「腎臓内科医の仕事はした」という功績なのかもしれない。重曹・カリウム吸着薬・高用量のループ利尿薬・降圧薬・MRAなどの工夫なのか。あるいは、選択バイアスなのか。いまは推察するしかない。
しかしその一方で、患者を死亡させたりMACEイベントに晒したりしているのなら、本末転倒である。
腎臓内科外来にいると、いわゆる「消えたCKD患者パラドクス(CKD3-4期のうち、腎代替療法が必要になる患者はわずかで、大多数は心血管系イベントでその前に死亡しているという統計結果)」の実感がわきにくい。
しかしこうした結果が出ている以上、安易にACEI/ARBは中止できない。する場合には患者に死亡・心血管系イベントのリスクを負うこと、透析を遅らせられる保証はないことを説明する必要があるだろう。あとは、STOP-ACEiスタディの結果を待ちたい。
②感想
待ちたい・・と書いたものの、STOP-ACEiスタディが進行中にもかかわらずこうした大規模解析が複数の国で行われる理由、それは「待てない」からだと思われる(こちらも参照)。「ルーチンに中止しない」KDIGOガイドラインの推奨と実臨床とのギャップを埋めたいのであろう。その背景について2点から考えたい。
1点目は医療の質である。「ACEI/ARB中断が医療の質を落としている」ということになると、QI(quality improvement)の進んだ国では医療政策に反映されるかもしれない。
たとえば米国には「コア・メジャー」があり、たとえば肺炎なら「来院X時間以内に培養・治療開始」が全例に守られないと病院への保険償還が減額される(例外はそのように明記しなければならない)。
こうした仕組みが多いのは入院診療であるが、いつかどこかのCKD外来で「ACEI/ARBが入っていますか(入っていないなら、その理由は何ですか)?」という問いが全例カルテに挿入されるようになるかもしれない。
2点目はコストである。「安価でエビデンスもありガイドラインで第一選択」のACEI/ARBは今後、糖尿病におけるメトホルミンのような立ち位置になっていくだろう。ジェネリックになっていない薬との合剤が出る日も近い?かもしれない。
CKD診療は新薬開発が進み、新規MRA・新規吸着薬(カリウム・リン・プロトン)・HIF-PH阻害薬・SGLT2阻害薬・バルドキソロンなどが参入してくるだろう。そんな中で、論文著者達は「(eGFRが30ml/min/1.73m2未満でも)まずはACEI/ARBを使いましょう」と言いたいのかなあ、と筆者は推察する。
以上、2つの論文を考察した。お役に立てば幸いである。