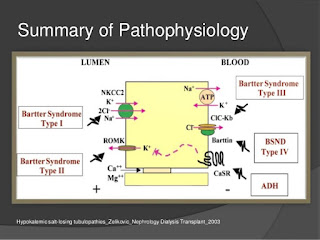今回は症例から酸塩基平衡異常と電解質異常について考えてみる。
症例:
50歳男性、経口血糖降下薬使用中で、COVID-19による呼吸不全で救急搬送。挿管管理が必要と判断され、救急外来で施行。胸部CT所見上は、両側肺野の陰影を認めARDS(急性呼吸急迫症候群)の所見が有り、集中治療室に入院。ノルエピネフリンとバソプレッシンを血圧維持に使用、鎮静目的でプロポフォールを使用した。
入院3日目に腎臓内科医が急性腎不全と代謝性アシドーシスにてコンサルト。
入院3日目データ (入院初日)
Alb 4.0g/dL (4.2)、Na 133 mEq/L (134)、K 3.8mEq/L(3.7)、Cl 97mEq/L(97)、HCO3 17mmol/L (23)、BUN 31 mg/dl (14)、Cr 1.7mg/dl (0.8)、血糖 133mg/dl (123)
コンサルトを受けて、何が異常と考えるか?
まずは、代謝性アシドーシスの悪化と新規の急性腎不全があることを異常と捉える。そして、おそらくは循環不全もあるので、その影響?と考える。
続いて何を検査するか?
*血液ガス検査を行う。
pH 7.14、pCO2 39mmHg、pO2 80mmHg、HCO3 17mmol/L
では、この血液ガス異常の解釈は?
① pH 7.14でありアシデミアの状態と判断。アシデミアの原因として、HCO3 16mmol/Lであり、代謝性アシドーシスによって起こされている。
② アニオンギャップはどうか? アニオンギャップ= Na- (Cl + HCO3)
なので、AG = 133 - (97 +17) →19
AG開大と判断する。
③ 代謝性アシドーシスに対しての呼吸性代償はしっかり働いているか?
予想pC02 = [(1.5 × HCO3) +8] ±2 なので、予想pCO2は30~34となり実測が39であり、呼吸性アシドーシスの併存があることがわかる。
④補正HCO3の計算(ΔAG/ΔHCO3でも可)。隠れた酸塩基平衡異常がないか?
補正HCO3 =実測 HCO3 + ΔAG
補正HCO3 = 17 + 7 →24であり、他の隠れた電解質異常はなし。
この症例の電解質異常はAG開大性代謝性アシドーシス+呼吸性アルカローシスとなる。
この症例のAG開大の原因は?
AG開大性代謝性アシドーシスの鑑別にGOLDMARK (LANCET 2008)がある。
Glycols (ethylene, propylene)
Oxoproline
Lactic acidosis
D-lactic acidosis
Methanol
Aspirin
Renal Failure – sulfate, phosphate
Ketoacidosis
Propofol Infusion Syndrome
この症例の場合の鑑別は?
・腎不全
・プロポフォール注入症候群(PRIS)
・糖尿病ケトアシドーシス
この症例では、血糖131mg/dLであり急性腎不全に加え、硫酸塩やリン酸塩の蓄積はなかった。βヒドロキシ酪酸: 2.9mmol/L。そのため、PRISが原因?と考えられた。
また、呼吸性アシドーシスに関してはCOVID19感染による影響が考慮された。
では、PRISとは何か?(参考資料はこちらがわかりやすい)
PRISは稀ではあるが、高容量のプロポフォールの使用によって引き起こされるものになる。48時間以上4mg/kg/hr以上の使用はリスクとなる。症状としては、徐脈や横紋筋融解症、代謝性アシドーシス、腎不全を引き起こし、死亡に至る。ATPが低下し、ピルビン酸が増加し、乳酸が増加する。
この症例では、乳酸の増加はなくPRISに関しては??となってしまった。
入院4日目:プロポフォールは中止
Na 148 mEq/L 、K 4.6mEq/L、Cl 108mEq/L、HCO3 16mmol/L 、BUN 33 mg/dl 、Cr 0.99mg/dl、血糖 210mg/dl
pH 7.17、pCO2 39.2mmHg、pO2 69mmHg、HCO3 16mmol/L
Anion-Gap: 24、βヒドロキシ酪酸: 6.9mmol/L
入院3日目から4日目で変化したことは?
・AGがさらに開大した。
・プロポフォール中止し、重炭酸製剤投与にかかわらず重炭酸濃度減少
・血糖上昇
・βヒドロキシ酪酸が増加 (2.9→6.9)
この時点での鑑別:
βヒドロキシ酪酸が増加、血糖も上昇していることからケトアシドーシスを考える。
頭の中では・・・
アニオンギャップはβヒドロキシ酪酸によって開大が考えられる。プロポフォールは24時間以上中止したが、改善乏しい。患者さんはもともと糖尿病の管理でSGLT2内服していたが、入院と同時にOFFにしてしまっていた。この症例の場合は正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスではないか?インスリン治療も開始してみよう。
インスリン投与後:
Na 153 mEq/L 、K 4.1mEq/L、Cl 111mEq/L、HCO3 26mmol/L 、BUN 43 mg/dl 、Cr 1.0mg/dl、血糖 176mg/dl
pH 7.43、pCO2 40mmHg、pO2 108mmHg、HCO3 26mmol/L
Anion-Gap: 14、βヒドロキシ酪酸: 0.9mmol/L
となった。
この症例の最終診断は、Euglycemic DKA (EDKA)
EDKAとは?
1973年にMunroらが211症例の正常血糖のケトアシドーシスが報告された。最近の報告だと、2017年に報告がある。EDKAの定義としては、血糖が250mg/dL未満で、アニオンギャップ開大性代謝性アシドーシスがあり、ケトン血症、ケトン尿になる。EDKAの原因は、SGLT2阻害薬の使用、来院前のインスリン接種、食事摂取制限、嘔吐などがある。SGLT2使用患者のCOVID19罹患患者のEDKAの5症例も報告されている。
あまり、個人的にはEDKAの概念を知らなかった。とても勉強になった。
今回のように、血糖が正常でもケトアシドーシスをきたしている例もあるということは、是非知ってもらいたいと思う。