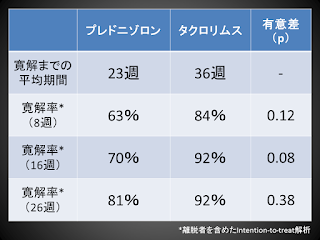Q1:どうしますか?
こんなとき、筆者は狭窄を拡張させるバルーンを用いて圧排していた。しかし往々にして、圧排だけでは血栓は除去できない。
血栓を除去するには、付着部のところから離断させるしかない。しかし、狭窄を拡張させるためのバルーンは「ツルツル」していて、血栓を「こそぎとる」力が弱い。ではどうするか?
そんなときにおススメなのが、「血栓除去用バルーン」だ。バルーン部分は摩擦係数の高いゴムで出来ている。本来は膨らませてから引き抜く道具だが、血栓の前後で「ゴシゴシ」していると、血栓を血管壁からはがすことができる。
ハッピーエンドだが、このように血栓除去に効果を発揮するバルーンカテーテルがあることは、その業界の方には常識であり、取り立てて書くまでもないほどだろう(筆者は最近まで知らなかったが)。そこで、二番目の質問に移りたい。
Q2:誰に感謝しますか?
まあこれも、血栓除去バルーンカテーテルが「フォガティー」と呼ばれていることを考えれば自明であるが、Thomas J. Fogarty先生(1934-)がこのカテーテルを開発するに至った経緯はあまり知られていないかもしれないので、紹介しておく(参考文献:英語版Wikipedia)。
フォガティー先生はオハイオ州シンシナティ生まれの米国人医師であるが、8歳で鉄道技師だった父親を亡くしてから、模型飛行機からスクーターのクラッチまで、いろいろ自分で作って売る生活をしていたという。
少年時代はボクサーになることを目標にしていたが、中学生時代に医療機器清掃のバイトをしていた病院で器用さを買われて手術助手の役目をしたりするうち、高校時代には医師を志すようになった。
学校の成績はよくなかったが、病院の恩師であるJack Cranley先生の助けもあって1960年にシンシナティ大学医学部を卒業。その在学中から、病院で多くの患者が下肢動脈塞栓から死亡するのを目にしていたため、侵襲の少ない血栓除去バルーンを開発していた。
まず彼は、(おそらく自宅の)屋根裏部屋で尿道カテーテルを触りながら、その先端に5.0サイズ手術用手袋の小指部分をつけることを思いついた。これで、原理的には、バルーン内に生理食塩水を充満させ、血管径まで広げて引き抜いてくれば血栓を除去できる。
バルーンとカテーテル(ラテックスとビニル樹脂)をくっつける接着剤が手に入らないのが問題だったが、彼は小さい時からフライ・フィッシングをしていたので、それを応用して両者を結んでくくりつけた。そして、ガラス管にゼリーをつめたモデルを用いた試行錯誤により、バルーンの血栓除去力と強度を工夫した。
彼はさっそくこれを企業に売り込んだが、最初の数年はまったく相手にされなった。しかし恩師のCranley先生は彼を励まし続け、シンシナティ大学で研修中はそこで外科医に自作のデバイスを使ってもらっていた。
1962年からはオレゴン大学に移ったが、そこの胸部外科部長のAl Starr先生が知り合いのエンジニア、Lowell Edwardsに実用化を持ちかけてくれた。1969年に特許を登録し、Lowellの会社で製造販売がスタートする。その会社こそが、Edwards Life Science社である。
この話には、成功の秘訣がたくさん詰まっている気がする。こうして日本語で書いておくことで、どこかで誰かがイノベーションを起こすきっかけになれば、うれしい。そんなわけで、フォガティー先生、ありがとうございます。
 |
| (出典はこちら) |