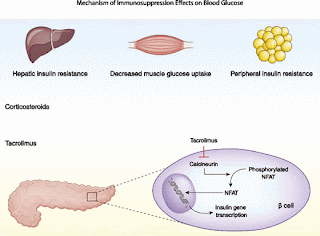今回はこのORGを整理していきたいと思う。
時間のない人は最初の「簡単なまとめ」だけを読んでいただければ概念はつかめると思う。
簡単なまとめ:
現在、CKD(慢性腎不全)は重大な社会健康問題になっている。
肥満もCKD発展のリスク因子であることが報告されている(KI 2017)。肥満により、糸球体還流が増加し糸球体の肥大を生じることでORGを起こし、タンパク尿や二次性FSGSを引き起こしCKD進行に寄与することが知られている(Nephron 2017)。
ORGはBMI≧30でFSGSの有無に関係なく糸球体肥大があれば診断される(Front med 2017)。
治療は体重を落とすということが一番の治療になる。体重を落とすということに関していえば、食事療法と外科的手術療法がある。
□肥満関連腎症の臨床症状:
蛋白尿の検出がもっとも典型的なパターンである(腎機能障害の併存がある場合とない場合がある)。
蛋白尿に関しては30%でネフローゼレベルの蛋白尿になると言われているが、多くの場合はネフローゼレベルの蛋白尿には至らない(KI 2001)。興味深いのは高度のネフローゼレベルの蛋白尿になっても、血清アルブミンの低下がない症例も多い。この理由は明確にはわかってはいないが、そのような症例ではβ2ミクログロブリンやNAGなどの尿細管障害マーカーの尿中排泄が低下していることが報告されている(NDT 2001)
その他に合併するものとして高血圧(50-75%)、脂質異常症(70-80%)と言われている。また、先に述べたようにネフローゼレベルの蛋白尿でも浮腫をきたすことは稀ではあるが、長期で見ると徐々に蛋白尿が増加し、末期腎不全に至る割合が10-33%であることが報告されている(KI report 2017)。
日本からも報告がでていて、20人の肥満関連腎症の2年フォローで7人の患者が腎機能の上昇を認め、2人(10%)が末期腎不全に至っている(CEN 2013)。やはり診断の遅れというのが一番の問題になるため、蛋白尿を手がかりに疑うことが非常に重要になる。
□肥満関連腎症の鑑別疾患と鑑別ポイント:
■高血圧腎症
・・高血圧腎症では糸球体のびまん性腎硬化が生じ、腎臓のサイズが正常腎に比べ小さくなる。硬化していない残っている糸球体はhypertrophyを生じるという特徴がある。高血圧と肥満は併存していることも多いが、中等度から高度血管病変に糸球体変化病変があった場合には高血圧性腎症を疑う。
■糖尿病性腎症
・・糖尿病性腎症では典型的にはメサンギウムの拡張と糸球体基底膜の肥厚所見を認め、これはORGの病変とは異なる。
■Primary FSGS
・・下記に表を記載するが、これは悩ましい。理由は先にも述べたようにORGによって2次性FSGSを生じるためである。
臨床所見では蛋白尿出現が緩徐でネフローゼレベルでない蛋白尿がORGによるFSGSの特徴である。
病理所見ではPrimary FSGSでは糸球体ボリュームが正常で、びまん性の足細胞の喪失所見が違いとして認められる。
 |
| Nat rev nephro 2016 |
ORGの病理所見:
これは、先に述べているが正常腎に比べてORGでは病理解剖などでも腎臓の大きさ・重さが大きくなっている特徴がある。その原因としては糸球体肥大が主要な要因である。観察研究で正常腎に比べて糸球体ボリュームが3倍くらいになっているが、糸球体密度は低いという特徴があった(CJASN 2012)。
FSGSに進展したものではPerihilar FSGSが一番多い。また、中等度巣状メサンギウム硬化、中等度糸球体基底膜肥厚化や尿細管基底膜肥厚化などの糖尿病様性変化(糖尿病の診断基準には至っていない)を認めるものもある。
電子顕微鏡では、主に足細胞の数の減少と中等度の足細胞の癒合が認められる。また、蛋白と脂肪の吸収顆粒がメサンギウム細胞や尿細管上皮細胞に認められる。
 |
□ORGの病因:下記の要因だけではないが、説明していく。
・血行動態の変化、RAA系、ホルモン反応不全・脂質代謝異常がメインの病因になっている。
■血行動態の変化
→腎血漿流量、糸球体灌流量の増加などを引き起こし糸球体腫大を生じる(Nat rev nephro 2012)。また、尿細管でのNa再吸収が亢進している。
■RAA系
→RAAS(レニンーアンギオテンシンーアルドステロン系)が亢進しており、それにともない循環動態の変化をもたらす(KI supp 2015)。
■ホルモン反応性不全、脂質代謝異常
→直接的、もしくは間接的に腎細胞の形態や機能の障害を起こし、糸球体腫大・糸球体数の減少をおこす(NDT 2013)。
+αの知識:
□肥満に伴う循環動態の変化
 |
| Nat rev nephro 2016 |
・輸入細動脈の拡張によるGFR増加、TGF(尿細管糸球体フィードバック)の減少によるGFR増加、RAASの増加などにより糸球体灌流増加により糸球体腫大・糸球体内圧の上昇をきたし足細胞の欠損が生じ二次性FSGSを生じる。
□脂質の異所性蓄積にともなうORG
メサンギウム細胞、足細胞、尿細管に蓄積することでORG発症につながる。
□ORGの治療
・体重を減らす
・・体重減少は蛋白尿の減少に寄与する。体重減少と比例して蛋白尿も減少する事が言われている。体重減少はカロリーの低下や減量手術で達成する必要がある。
・RAAS阻害薬
・・肥満を伴う蛋白尿患者では蛋白尿の減量を認め、十分効果が認められている(Curr hyperten Rep 2015)。
・血糖降下薬
・・DPP4阻害薬やGLP1受容体作動薬などのインクレチン関連治療は高脂質によって発症したORGの発展を抑制したことがネズミの実験でわかっている(Am J Physiol Renal Physiol 2018)。
メトホルミンに関しては腎の線維化を抑制する可能性が示唆されているがはっきりとはしていない(Nephron 2018)。
・脂質代謝調整の治療
・・ネズミの実験でINT-777というTGR5受容体の選択的作動薬が蛋白尿を減らし、足細胞障害、メサンギウム拡張、線維化を障害し、マクロファージの腎の発言が減少したことが報告されている(JASN 2016)。また、ミトコンドリアの発生を生じ酸化ストレスも減少したと報告している。
Lipoxin A4というIL-12の産生を減少させる重要な因子がORGマウスに対してNF-κBとERK/p38 MARK経路の活性阻害によって、腎の炎症を抑えることが報告され、将来的な治療に注目されている(Life sci 2018)。
・新規治療
・・SS31というミトコンドリアに対しての抗酸化作用をもつものが、糸球体の内皮細胞や足細胞の保護をして、メサンギウム拡大、糸球体硬化、マクロファージの流入、炎症因子や脂肪による毒性からのミトコンドリア障害を防ぐことがわかり、ORGの治療薬への期待がある(KI 2016)。
亜鉛がP38 MARK関連炎症反応を低下させ、ORGの進展抑制が報告されている(Obesity 2016)。
クルクミン(ウコンなどに含まれるポリフェノール化合物)がWnt/β-catenin経路を阻害することによって足細胞に対するレプチン毒性を減少させ、これがORgの治療に寄与するのではと考えられている(Evid based Complement Akternat Med. 2015)。
下の2つはORG患者の治療になりうる可能性があると考えられている。
・mTOR阻害薬が腎臓への脂肪蓄積を抑制させるのに有効であると報告がある(Lancet Diabetes Endocri 2014)。
・選択的エンドセリンA受容体阻害薬は糖尿病患者の尿蛋白減少と腎機能保護に寄与することが報告されている(Lancet 2019)。
なので、治療に関しては現時点では体重コントロールというのがメインにはなってくる。高血圧があればRAS阻害薬、DMがあればDPP4阻害薬やGLP1作動薬を選択することがプランになるのではないか。
もちろんORG単独の治療だけでなく、ORGを発症しやすい患者では心血管合併症も多くなりうる。そのためASCVD riskは計算しておく必要性はあり、それに対しての積極的な介入も行うことは非常に重要となりうる。