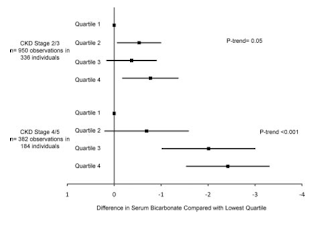同じ食塩量を摂っていても、アルドステロンとコルチゾンの1日排泄量(それぞれUAldoV、UCortisoneV)には波がある。高い日と低い日の差は、6g/d食でも9g/d食でも12g/d食でも大体同じで、UAldoVは7.6mcg/d、UCortisoneVは33.8mcg/dだった。
UAldoVが多い日は、少ない日にくらべて飲水量がおおく、尿量がすくなく、水がたまった(体重も増えた)。ここでも、以前に
書いた、尿浸透圧と尿量の変化から自由水どれだけたまった(または、捨てられた)かを計算する方法をつかっている。
いっぽう、6g食から12g食にするとUAldoVは減る(平均5.1mcg/d)。上記変化はUAldoVが7.6mcg/d増えた結果なので、UAldoVが5.1mcg/d減った影響は上記に5.1/7.6を掛けて正負を反転させたものになるとグループは考えた。
同様のことをUCortisoneVでもおこなうと、次のようになる。6g/d食から12g/dになってコルチゾンはふえるので、今回は正負が反転しない。ここでUAldoVの時と違う点のひとつは、体重が減らなかったことだ。コルチゾンがふえて自由水が捨てられたのに、飲水量がかわらないのだから、体重は減りそうなものだが減っていない。
これをみてグループは、捨てられた自由水は内因的に作られた水、つまり代謝水だと推察している。食べ物から余計に水が作られれば、飲み水が増えなくてもいい。たしかに糖質コルチコイドには異化を亢進する作用があるから、それでいいのかもしれない。
では、アルドステロンはどのように尿量をへらし、コルチゾンはどのように尿量をふやすのか?それを調べるのに、グループはそれぞれのホルモンが高い日と低い日の尿中溶質排泄と浸透圧をくらべてみた。
するとアルドステロンが低い日は、高い時にくらべて尿Na排泄量(UNaV)がふえたが、尿K排泄量(UKV)は減り、尿素排泄量(UUreaV)も減ったので全体の溶質排泄量はかわらず、尿浸透圧はさがった。いっぽう、コルチゾンが高い日は、低い日にくらべてUNaV、UKV、UUreaVいずれもふえたが尿浸透圧はさがった。
これらの現象でいまのところわかっているのは、アルドステロンがさがるとENaCによるNa再吸収がおちて、それに付随しておこるROMKによるK排泄も減ることくらいだ。これをグループはTraditional natriuretic conceptと呼んでいる(図)が、伝統的というだけあって目新しいことではない。RAA系ということだ。
いっぽう、アルドステロンと尿素、糖質コルチコイドとNa、K、尿素の関係は、これから調べられるフロンティアだ。これを説明するのに、このグループは伝統的なコンセプトにかわるAlternative natriuretic-ureotelic conceptというコンセプトを提唱していて興味深い(図)。
なお「-telic」はテロメアのテロと同語源で終末を意味するから、ureotelicとは尿素で終る、つまり「尿素排泄の」ということ。それに対して窒素の最終排泄物がアンモニアの場合をammonotelic、尿酸の場合をuricotelicという(それぞれ魚、鳥など;図はJournal of Experimental Biology 1995 198 273を改変)。
Alternative natriuretic-ureotelic conceptは、ふえた塩分を排泄するとき一緒に水を失わない合理的な仕組みといえる。RAA系だけでは、塩分がふえるとENaCを介したNa再吸収が減って水が失われてしまう。しかしそれに平行して腎髄質の間質に尿素が蓄積し水を引き、抗利尿に働くかもしれない(推測)。また糖質コルチコイドの働きで代謝水がふえ、飲水量をふやさずに済むかもしれない(推測)。
これらのメカニズムはいまだ不明だが、糖質コルチコイド作用がたかまってたんぱく異化により尿素が増えているのかもしれない(推測)。髄質への尿素の汲みだしには、UT-A1が関与しているかもしれない(推測)。
さらに、鉱質コルチコイドと糖質コルチコイドが自由水の管理を互いに拮抗する働きを持ち、どちらも周期的にゆるやかに上下を繰り返していることから、両者はあたかも交感神経と副交感神経、RAA系とプロスタグランジンのように調節しあっているのかもしれない(推測、図)とグループは提唱する。
このモデルによれば、鉱質コルチコイドがふえると塩と水が身体にたまる(図の環が6時から12時にまわる)。すると今度は糖質コルチコイドが増えて塩と水を捨てる(環が12時から6時にまわる)。塩分摂取がすくなければ塩と水を守る方向、すなわち鉱質コルチコイドが優位になる(図の左半分)。塩分摂取がおおければ逆で、糖質コルチコイドが優位になる(図の右半分)。
推察ばっかりだが、糖質コルチコイドが体液バランスにおよぼす影響や、尿濃縮に大事な役割をもっているのにいままで(電解質でないためか)あまり掘り下げられてこなかった尿素の仕組みについて考えるきっかけになった。バソプレシン(と血漿浸透圧)を考えなくてもここまで説明できるのは、目からウロコだった。
ここまで推論したら、あとは実証すればいいというわけで、JCI5月号にもうひとつ載った論文(JCI 2017 127 1944)がそのアンサーソングになっている。これは、べつに紹介する。もしこれからこの領域の知見が増えてくれば、高血圧や腎疾患などの診療が別次元に深まるのかもしれない。UT-A1阻害薬(Nat Rev Nephrol 2015 11 113)とかそういうレベルではなく、それこそ「火星に人が着陸する」くらい、変わるかもしれない。それにしても、宇宙開発はその過程でいろんな科学の副産物をもたらしてくれる。