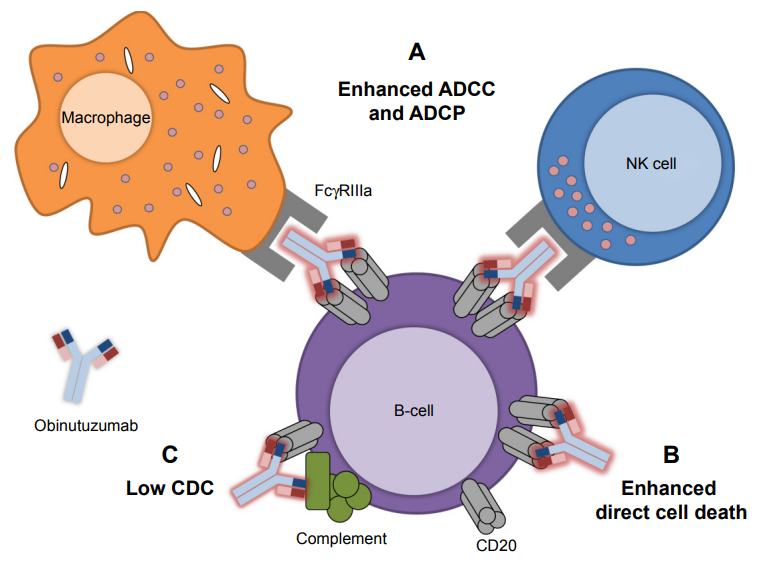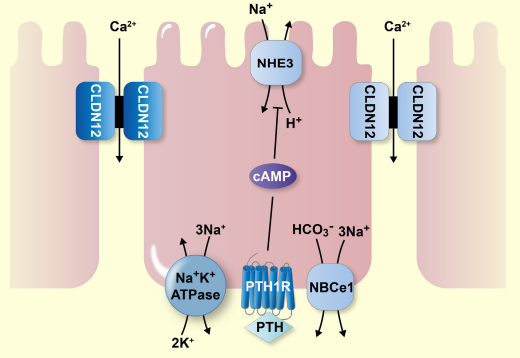2017年、2019年、2021年に興奮と共に紹介してきた経口C5a受容体阻害薬、アバコパン。日本でも2022年6月に販売が開始されたが、残念ながらゲーム・チェンジャーになるほどANCA関連血管炎でどんどん使われてはいなかったように思われる(あくまでも2024年4月までの筆者の印象)。
 |
| (出典はこちら) |
理由を推察するに、①長期使用データが乏しいこと、②使用期間が明記されていない(維持レジメンのデータがない)などだろうか。③薬価は新薬で必ず懸念される要素だが、患者の多くは特定疾患対象であり、少なくとも自己負担は生じないはずだ。
そんななか、①についてのリアル・ワールド・データが2024年に発表され(KI Rep 2024 9 1783)、②については維持レジメンとしての使用が治験中(NCT06072482)であることを知った。それぞれ少し紹介したい※。
※筆者はこの投稿に利益の相反を持たない。
・リアル・ワールド・データ
米国の12医療機関で、2021-2023年に、ANCA関連血管炎に対してアバコパンの治療を受けた、92例(新規61、再発32)の患者が対象で、平均フォローアップ期間は6ヵ月と短め。平均年齢59歳、女性64%、白人82%、MPO-ANCAが72%であった。
約8割に腎病変があり、平均eGFRは32ml/min/1.73m2、eGFR15未満が23%、透析依存が10%、平均蛋白尿は1.6g/g、腎生検を受けた48例のうち半月体タイプは37%だった。また、約半数に肺病変が見られた。なかなか重症である。
それもあってか、寛解導入レジメンはRTX+低用量CYCが47%、RTXが48%(その他、通常用量CYCが2例、MTXが1例、ステロイドパルスのみが1例)。また、14%で血漿交換が用いられた。ステロイドパルスは64%に使用された。
アバコパンは平均3.6週(四分位範囲2.1-7.7)目から開始され、アバコパン開始から平均5.6週(四分位範囲3.3-9.5)でステロイドが漸減されていた。26週時点の平均プレドニゾン用量は1.8mg/d、52週時点の平均は0.6%であった。
また、60%の患者がDay 30までにアバコパンを開始され、40%の患者がDay 31以降に開始されていた。遅く始まった患者の方がeGFRが低く、血漿交換を受けた患者が多かった。eGFRの回復が遅めであったのは、アバコパンのためかもしれないし、それだけ重症だったためかもしれない。
なおアバコパンは99%タンパク結合のため、透析では除去されないが血漿交換では除去される。ただしアバコパンの分布容積は345Lもあるので、そこまで問題にはならないかもしれない。
それで、「治療医師の裁量」による26週後の寛解率は90%であった。より客観的には、eGFRが平均12.2ml/min/1.73m2上昇し、血尿が68%で消失し、蛋白尿が平均0.4g/gに改善していた。スタディ開始時に透析を要した9例のうち5例が透析を離脱したが、2例が透析後に透析依存となっていた。
また、臨床的な再発は3%、入院を要する感染症は13%、死亡は4%であった(卵巣がんが1例、COVID19が3例)。有害事象による内服中止は20%に見られ、肝障害(4例、うち2例で肝酵素が200-500U/l程度まで上昇)・消化器症状などが主な理由であった。
・維持レジメンとしての使用
アバコパンがリアル・ワールドでステロイドの累積使用量を減らして患者のためになっているのは素晴らしいことである。だが、せっかくfirst-in-classで出てきた薬であり、1年間※と言わずもう少し出番はないだろうか?
※ADVOCATEが52週の使用であったため。UpToDateにも「52週を越えた有効性と安全性は確立されていない」とある。ただし、前述データでは、52週でアバコパンを完了していたのは12%であった。(それと中止された20%を除く)68%は52週以降も使用されていたようである(その期間は不詳)。
・・となると、維持レジメンとしての使用はどうかという話になる。現在ANCA関連血管炎の維持レジメンといえばRTXが定番で(前述のデータでは98%がRTXであった)、MAINRITSAN 3スタディで長期の寛解維持も示されている。
しかし、RTXにも問題がないわけではない。たとえば、B細胞の慢性的な除去による低ガンマグロブリン血症は、感染症などのリスクとなる。そこで、MAINRITSAN 3のように6ヵ月ごとが本当に適切なのかが研究されている。
その一つ、MAINTANCAVASスタディ(Ann Rheum Dis 2024 83 351)は、6ヵ月ごとのRTXで2年の寛解を維持した患者をB細胞が戻ってきてから打つ群とANCA抗体が戻ってきてから打つ群に分けて比較した。
その結果、約4年間で平均3.6gのRTXを受けたB細胞群は、平均0.5gのRTXを受けたANCA群に比べて寛解率が有意に高かったものの、COVID-19感染も有意に多く、うち2例が死亡していた。中間の2g(1年に0.5g)くらいがちょうどよいのだろうか?今はまだ、わからない。
そんなわけで、アバコパンを長期使って維持してはどうか?というのが治験である。プラセボ対照で「標準治療(standard of care、SOC)+アバコパン30mg1日2回60か月」と「SOC+アバコパン30mg1日2回12か月(残りはプラセボ)」と「SOC+プラセボ60か月」を比較するという。
SOCはその施設の裁量であるため、多くがRTXになってしまうだろう。あるいは「実薬かもしれないから弱めのレジメンにしよう」となるかもしれない。この治験が終わったら、今度はRTXとの比較対照試験が始まるかもしれない。
患者にしてみれば、「6ヵ月(あるいは1年)に1回注射」のほうが「3カプセル1日2回の薬を5年間内服し続ける」よりも便利かもしれない。ただ、寛解維持率や感染リスクの点でRTXより優れていると分かれば、選択肢になるだろう。
【訂正】以前の稿で、アバコパンの使用開始時期と使用期間を誤って記載していました。お詫びします。