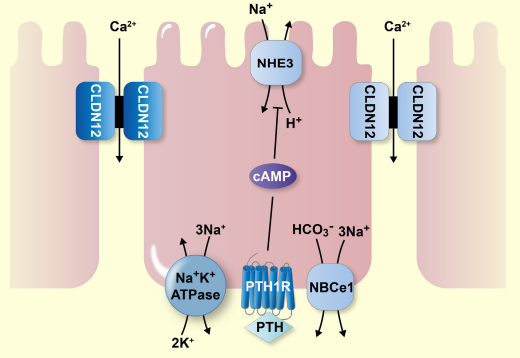3.切替(conversion)
CNIベースの維持免疫抑制レジメンで拒絶が起きないのはよいが、残念ながら腎機能低下・さまざまな心血管系イベント・悪性腫瘍などの副作用があり、それらは「拒絶さえしなければよいだろう」と無視できるものではない。そんな時にはCNI-sparingレジメンが考慮され、筆者が以前米国にいた2011年にはもっぱらmTOR阻害薬が用いられていたが、今の米国はbelataceptが主流である。
こうした使用はCNIを続けることが望ましくない場合やde novo DSAが出現した場合に限って症例ごとに退避的に行われる"rescue therapy"がほとんどであり、エビデンスの質は後方視になりがちで高くない。それでも、eGFRやグラフト予後の改善が見られたという報告や、急性細胞性拒絶に有意差がなかったという報告は散見される。切替が術後何年も経って行われることも影響しているだろう。
なお切替方法は施設・医師・患者ごとにまちまちであり、よく保険が通るなと思うほどであるが、一応準拠するレジメンはある。それは"per protocol"の切り替えを行った多国籍の第3相RCT(JASN 2021 32 3252)で、belataceptは5mg/kgを2週間ごと5回行い、以後は4週間ごとというものだ。CNI(90%がtacrolimus)は4週間で漸減終了した。
結果は24か月でグラフト予後に有意差はなく、eGFRは切替群で有意に高く(55.5 v. 48.5 ml/min/1.73m2)、de novo DSAは切替群で有意に低く(1% v. 7%)、急性細胞性拒絶は切替群で有意に高かった(8% v. 4%)。
4.CNI with belatacept
ここまでくると、誰もが①CNIとbelataceptの「いいとこどり」はできないか?、②Belataceptで拒絶する患者のリスク因子は何か?などと考えたくなるだろう。そんなわけで、①については「CNI+belatacept」のレジメンをよく見かける。Belataceptは5mg/kgだが、ローディングは3回なこともあるし、維持量も1-2か月に1回などまちまちである。また、tacrolimusの目標トラフは通常4-6ng/mlのところを3-5ng/ml、といった具合である。
要は"little bit of both"である。こうなってくると、もはや前向きに有効性を評価することはできないが、医師裁量が広く使いやすくなったとも言える。個人的に心配なのは、「ステロイドとMMFとtacrolimusとbelataceptだと4種類(quad)になってしまう」と言って、割とあっさりMMFが中止されることである。なんとなく、MMF+CNI+belataceptのほうが拒絶しにくくステロイドの副作用も減らせて一石二鳥、と思ってしまう。
5.Patients at risk
前項②については、免疫学の深みにはまってしまうので、これまた「Thymoで導入したから安心して切り替えられる」とか経験則に基づきがちであるが、せっかく抗CD28の治療と分かっているのだから、T細胞のサブセットやマーカーによってbelataceptで拒絶しやすい群を同定できないかという試みは行われている。
たとえば、移植前に「CD28+、CD8+のTEMRA細胞(ナイーブT細胞に見られるはずのCD45RAが、いちど消えた後で再び発現している段階)が3%以上」、「CD57+(NK細胞にも見られるマーカー)、PD1-のTEM細胞(effector memory T cell)が多い」などの群である。この辺りの理解が深まると「それなら抗〇〇抗体を併用すれば拒絶が防げるのでは?」といった話にもなってくるが、今はまだ実用的ではない。
なお、免疫学の深みもさることながら、よく知られたbelataceptの禁忌はEBV陰性である。HIV感染、CMV血症なども慎重投与である。術後のFSGS再発などで血漿交換を行っている場合にも、belataceptは抜けてしまう。また、COVIDワクチンは、belataceptを打ってしまうとその効きがとても悪くなる。
6.おわりに
筆者は「もうこれは(いろいろ問題もあるけど)やるもんでしょ」という治療に対して、「本当にそうだろうか、それ以外のよりよい方法があるのではないか、全員とは言わないが、他の方法でうまくいく状況と患者がいるのではないか?」と考えてしまうタイプである。その代表がステロイドと透析だった。CNIもまた、40-50年の時を経て「素晴らしい薬だけれど・・問題もある」という場面を迎えていると感じる。
こういう薬や治療は、それはそれで確立しているわけだから、全員がいきなり乗り換えるような新しい治療は生まれにくい。それでも、「何かあるんじゃないか、きっとあるはずだ」と考え続けていれば、徐々に変わっていくと思う。※筆者はPrograf®(tacrolimus)、MeltDose technologyで徐放化に成功したEnvarsusXR®、Nulogix®(belatacept)の製薬会社と、利益の相反を持たない。
 |
(Bella Notte、出典はこちら)
|